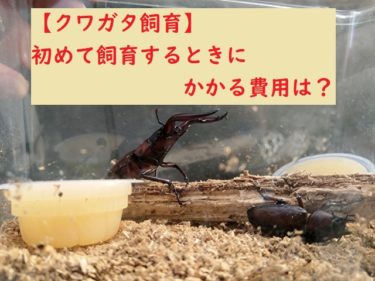こんにちは。ケンスケです。
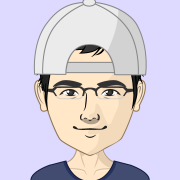
私は毎年、国産クワガタを産卵させて、幼虫飼育・羽化・成虫飼育を楽しんでいます。
で、クワガタの幼虫飼育には「菌糸ビン」をよく使います。
菌糸ビンで飼育する理由は、
簡単だから!
マット飼育(ボトルに詰めた発酵マットで幼虫を飼育)だと、
ガス抜き
マット詰め作業
加湿
こういった作業を幼虫の数だけやらなくてはならないんですね。
やっぱり数が増えてくると作業量も年々増加。
【菌糸ビン飼育】だとこの作業がかなり少なくなるんです。
簡単で失敗も少ない菌糸ビンでのクワガタ幼虫の飼育ですが、気をつけてほしいことがいくつかあります。
この記事では、
菌糸ビン交換のやり方
注意事項とコツ
について解説していきます。
菌糸ビン飼育とは?こちらの記事もご一緒にご覧ください。
こんにちは。ケンスケです。 私が子供の頃、クワガタの幼虫を飼育するのは、なかなか敷居の高いものでした。というのは、現在のように飼育方法が確立されておらず、「材飼育」が基本となっていたのです。「材[…]

『【クワガタ幼虫飼育】菌糸ビン交換と管理。タイミングに気をつけよう!』
菌糸ビン交換の時期。
まずは交換が必要な時期について解説していきます。
交換するタイミングは重要になってきますので、覚えておきましょう。
②購入して3ヶ月(夏場は2ヶ月)
③菌糸ビンの劣化
①食痕が6~7割になったら。

クワガタが菌糸ビンの中を移動すると、その部分の菌糸が壊れてオガクズの色に変わります。
この場合は、時間が経ってまた菌糸が回ってくると新しい菌糸ビンのように色が白く戻ります。
また、クワガタの幼虫が菌糸に分解されたオガクズを食べた痕は、「食痕」とよばれ、黒や茶色(クワガタのフンや分泌物の色)になります。これには菌糸が回らないので時間が経っても黒や茶色のままです。
だいたい使用されるボトルは透明か半透明のものなので、食痕が外から見てわかりやすいです。
これが表面の6~7割を占めてくるようなら交換時期です。
②購入して3ヶ月(夏場は2ヶ月)

クワガタの幼虫によっては「居食い」で、外観からは食痕が分かりづらいことがあります。
クワガタの幼虫があまり移動せずにビン内部で自分の周囲のオガクズを食べることがある。
ビンの外側から食痕が見えないので不安になるが、移動しない分エネルギー消費が抑えられて、大型化も期待できる!
そんなときはだいたい2~3ヶ月で交換します。
なぜかというと、ビン内部のオガクズは3ヶ月程度で、菌糸によって分解され尽くすからです。
それ以上経過すると、置かれた環境にもよりますが内部のマットの劣化が顕著になってきます。
菌糸ビン内部の劣化は、「羽化不全」や幼虫の「病気」にもつながるので、食痕が少なくても交換しておきます。
※冬場(気温が15℃を下回るぐらい)は交換は控えましょう。
理由は後ほど説明します。
③菌糸ビンの劣化

幼虫を投入してから3ヶ月経過していなくても、菌糸ビンの劣化が見られたら交換しておきます。
○ビンの色が黄色っぽくなってくる。
○ビン内部に食痕とは違う黒い根のようなものが広がる。
○全体が茶色がかってくる。
他には菌床自体が縮んで、ビンとの隙間に水分が出ることがあります。
中が分解されて水分を排出していたり、隙間に結露がたまったりしていると考えられます。
多少なら気にしないでも大丈夫ですが、食痕が水分を吸収するとそこから雑菌が繁殖することがあるので、交換を早めてもいいかもしれませんね。
カビが生える。
青いカビが生えてくることもあります。それほど問題はありませんが、上部にある場合は削って除去します。白い部分にまで広がるようであれば交換します。
3齢後期の幼虫の交換は慎重に。

幼虫が大きくなって、しばらくすると蛹室を作り始めます。
蛹室とは、幼虫が蛹になる空間で、菌糸ビン内部につくります。
この「蛹室」を破壊してしまうと「羽化不全」の危険が高まります。蛹の時期はとてもデリケートで、クワガタは移動も食事もできません。
初期の蛹の中はドロドロになっているのです。
問題は「前蛹」状態のとき。
クワガタは前蛹になる前に蛹室を作ります。
前蛹になったあと、蛹室を壊してしまうともう一度蛹室をつくることはできません。
だいたい2回目か3回目の交換の時期が重要
どうやって判断するかというと、
外側から見て蛹室を見つける!
菌糸ビンに使われるボトルは、だいたい透明か、半透明。
クワガタがボトルの外側部分に蛹室を作ってくれれば、見つけやすいです。
ただし、ボトルの内部に蛹室を作ってしまうと外側からは見えないんですよね。
ここが難しいところ。
緊急な事態でなければ、1~2週間そのままの状態で毎日観察してみましょう。
まだ、蛹室を作っていなければ坑道(クワガタが移動した痕)やクワガタ幼虫の姿が見えることがあります。
それでも内部の様子がわからなければ、慎重に掘り出してみます。
もう自力で蛹室を作り出すことはないので、「人工蛹室」にて管理します。ビンの外側から蛹室が確認できても、蛹室内にキノコが生えていたら、「人工蛹室」に移しましょう。
普通に交換して大丈夫です。
幼虫が大きく黄色っぽく(クリーム色っぽい)なっていれば、次の菌糸ビンで蛹室を作るはずです。
幼虫が黄色っぽい色になり、皮膚のツヤがなくなって、足が縮こまるようになります。
蛹になる直前です。

国産のクワガタの幼虫は種類によっても異なりますが、
オス 8~12ヶ月
メス 6~10ヶ月
で蛹室をつくって蛹になります。
菌糸ビンにラベルを貼って、生まれた月や体重、交換した日付を記入しておくと、幼虫の状態を推測する手がかりになります。
クワガタ幼虫の雌雄を鑑別する方法! こんにちは。ケンスケです。クワガタを幼虫から羽化させるのに、オスとメスでは使用するケースの大きさや菌糸ビンの交換回数が違うこともあります。そんなとき、「幼虫のうちから雌雄を判別できたらいいなぁ。」って思います。今[…]
クワガタの「~令」を見分ける方法。
こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタの幼虫って、孵化したてはほんとにちっちゃいですよね。でも、冬が明けてマット交換をしてみると長さも10センチを超えるぐらいの大きさになっていてびっくりしたことはありませんか?[…]
菌糸ビン交換のやり方。
 こんな道具を用意しておくと便利ですよ!
こんな道具を用意しておくと便利ですよ!
それでは、実際に交換の方法をみていきましょう。
②新しい菌糸ビンの上部を削り穴をあける。
③古い菌糸ビンから幼虫を取り出す。
④幼虫を観察する。
⑤新しい菌糸ビンに幼虫を投入。
⑥幼虫が潜るのを待つ。
こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタが蛹から羽化したら嬉しいものですよね。ついつい触ってみたり、持ち上げてみたりしてみたくなっちゃいます。でも、ちょっと待ってください!羽化後まもなくは、まだ身体[…]
①新しい菌糸ビンの温度を合わせる。

お店では菌糸ビンは「冷蔵庫」など冷暗所で保管されています。
15℃を超えてくると菌糸の活動が活発になりやすいからです。
そのまま幼虫を入れてしまうと温度差によって、ダメージを受けてしまうことも考えられます。
1~3日飼育場所と同じ環境に置いて、温度を合わせておきます。
②新しい菌糸ビンの上部を削り穴をあける。

ボトル内部では網の目のように菌糸が根を張ります。幼虫がボトル内部を掘り進むことによって、菌糸ネット(菌糸が伸びている)壊されます。
そうすると菌糸が再生しようと活発になるので多くの酸素を必要とします。
クワガタにとって酸欠になりやすいんですね。
なので、通気を良くするためにボトルの肩口ぐらいまで思い切って削っておきます。
上部にキノコが生えてきて通気孔を塞いでしまうまでの時間稼ぎもできます。
上部を削り取ったら、幼虫よりも少し大きな穴を開けます。
クワガタが潜りやすくするためですね。
③古い菌糸ビンから幼虫を取り出す。

幼虫の入ったボトルから幼虫を掘り出します。
オガクズは固く詰めてあるので、力が必要ですが、幼虫を傷つけないように気をつけて慎重に行いましょう。
坑道(クワガタの通り道。周囲と色が違う)をたどっていくと幼虫を見つけやすいですよ。
④幼虫を観察する。

掘り出した幼虫をよく観察してみましょう。基本的に地中に潜っている幼虫を観察する機会はあまりありません。
このときに多くの飼育者の方々は体重測定をしています。
オス・メスを見分けたり、大きさを推測したり、蛹化のタイミングを見極めたりするのに役立ちます。
飼育の統計をとったりするのもおもしろいですね。
⑤新しい菌糸ビンに幼虫を投入。

新しい菌糸ビンの穴に幼虫を優しく入れます。
幼虫は素手で触らないようにしましょう。菌糸や幼虫は雑菌に弱いためです。
頭が穴の底にくるようにうまく入れてあげると、幼虫も潜りやすいですよ。
⑥幼虫が潜るのを待つ。

幼虫が新しい環境に馴染めるかを見極めるために、潜っていくのを見守りましょう。
元気がなかったり、新しい環境が気に入らなかったりすると潜らないこともあります。
潜るまでは今までの菌糸ビンも捨てないようにしておきます。
国産クワガタの必要な菌糸ビンの本数の目安。
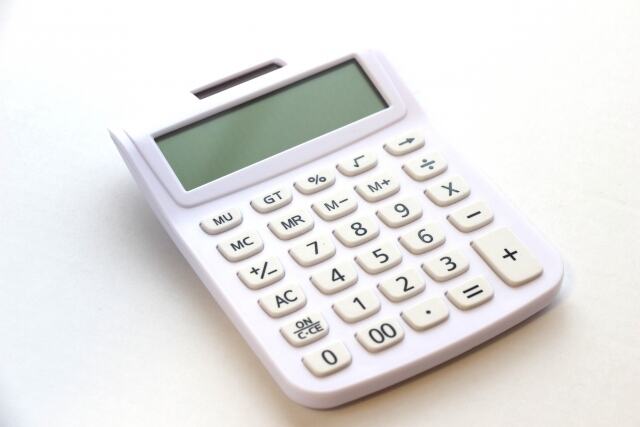
菌糸ビン交換の方法がわかったところで、気になるのが、その交換の回数。
今回紹介するのはあくまで、「目安」です。
クワガタがたくさん食べたり、菌糸ビンの劣化が早かったりすると多くなることもあります。
オス3本
メス2~3本
オス2~3本
メス2本
オス2本
メス1~2本
オス2~3本
メス2本
これぐらいでしょうか。
実際の必要本数は、クワガタの状態や飼育環境に応じて変わります。
よ~く観察して、交換時期を見極めてみてくださいね。
こんにちは。ケンスケです。初めてクワガタを飼育するときに気になるのが、飼育にかかる費用ですよね。お子さんがカブトムシ飼育を始めたのをきっかけに、親御さんのほうが昆虫飼育にハマってしまった!っていう話もよく聞きます[…]
交換時の注意とコツ。
いろいろと注意事項はありますが、簡単にいうと、
清潔に・丁寧に・愛情をもって扱えば問題ないですよ!
菌糸はデリケート。
菌糸は雑菌に弱いです。
扱う時は素手で触れないようにして、使う道具(スプーン)はきれいに洗って、よくすすいでおきましょう。
温度も大事です。10℃~20℃はキノコが生えやすい温度帯。
もとはキノコを生やすために作られた菌糸ビンですので、生えるのは問題ありませんが、出てきたらその都度除去しましょう。
(通気孔を塞いだり、栄養をとられたりするので。)
 保管していた菌糸ビンからキノコが!通気孔を塞いでしまっています。幼虫が入っていたら危険!
保管していた菌糸ビンからキノコが!通気孔を塞いでしまっています。幼虫が入っていたら危険!
衝撃も厳禁です。
衝撃で菌糸が壊れると、菌糸を再生するために酸素を多く消費します。ボトル内部が酸欠になる恐れもあります。
幼虫もデリケート。
クワガタの幼虫も繊細です。
地上は、地中とは違う雑菌が多くいます。素手も同じです。
また、人に慣れることもないので、いじくり回されると多大なストレスを感じることでしょう。
掘り出したら早めに新しい菌糸ビンに入れてあげることで、ストレスを軽減してあげましょう。
屋外で作業をする時は?
温度・直射日光に注意しましょう。
菌糸ボトル内部は外気温より2℃ぐらい高くなっています。
寒いところではあまり作業しないほうがいいですね。
直射日光も幼虫には有害です。ほんの少しの時間なら問題はありませんが、長く日光を浴びすぎないほうがいいですね。
とくに春から夏場の日光はかなり暑いです。幼虫にダメージを与える前に手早く作業しましょう。
猫やカラスにも注意。
幼虫は野生動物にとってはエサ。
幼虫を掘り出したまま、その場を離れたスキに襲われることも考えられます。
海に近いとトンビも狙っています。
我が家は夏場、ハンミョウやアリがいて、屋外で作業するといつの間にか幼虫を襲おうとしていたりもします。
気をつけましょう。
菌糸ビン交換後の「暴れ」。
菌糸ビンを交換後、幼虫がボトル内を動き回ることがあります。
原因は酸欠だったり、居場所をほぐすためだったりします。暴れると菌糸がまた再生しようとしてさらに酸欠になることも。
そんなときは、
ビンのフタを開けて通気性をよくする。
または
ビンを逆さまにしておく。(二酸化炭素を排出する)
これで1~2週間様子をみます。
それで落ち着いてくれれば問題ありませんが、幼虫が上に出てきてしまったり、元気がないときは「マット飼育」に切り替えましょう。
クワガタの幼虫の「暴れ」について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。 こんにちは。ケンスケです。クワガタ幼虫が「暴れる」って聞いたことありますか?この「暴れ」、幼虫が飼育ケースの中をメチャクチャに移動してしまう行動のことをいいます。で、なにが問題なのか?というと、「[…]
冬場(気温が15℃を下回ったら)は交換しない!
幼虫は気温が15℃を下回るとあまりエサを食べず、移動もしなくなります。
この時期に交換してしまうと、幼虫に大きな負担になってしまいます。
食べられないのに「体力を消耗」してしまうからです。
ただし、15℃以下でも菌糸ビンは劣化するので、交換が必要な時はしばらく暖かい部屋において、クワガタの活性をあげてから行うといいですね。
クワガタ幼虫の管理。

菌糸ビンに限ったことばかりではありませんが、クワガタの幼虫を飼育するときの注意を確認しておきましょう。
項目が多くなってしまいましたが、基本的なことなので頭に入れておくと安心ですよ。
温度に気をつける。
国産クワガタの飼育温度は、種類にもよるのですが、
5℃から28℃まで
と考えてください。
菌糸は高温になると急激に劣化し、幼虫も高温には弱いです。
とくに夏場は30℃以上の環境が長時間続かないように気をつけてください。
温度変化が大きい場所や明るい場所も避けましょう。
衝撃に気をつける。
衝撃は、菌糸にダメージを与えます。そうすると菌糸の再生が活発になり、菌糸ビンの劣化が早まります。
幼虫も衝撃に弱いので菌糸ビンは丁寧に扱いましょう。
菌糸の劣化。

クワガタが成長する温度は、菌糸も活発になる温度です。
どうしても菌床の劣化は避けられません。
黄色・茶色・黒っぽくなってきたら、劣化の合図です。
菌床が縮んできたり、カビも交換が近づいているサインになります。
劣化した菌床は、成長障害だけではなく、病気のもとにもなるので、交換時期を見極めましょう。
幼虫の様子を観察。
交換したときしか幼虫をよく観察する機会はありません。
「皮膚の状態をみる」、「大きさを確認する」などしっかり成長を感じておきましょう。
 右側の幼虫がブヨブヨ病と思われる。
右側の幼虫がブヨブヨ病と思われる。
ブヨブヨ病…幼虫が透明になり、エサを食べなくなる。
黒点病…皮膚に黒い斑点ができる。
両方とも劣化した環境が原因といわれています。すぐに菌糸ビンを交換して様子を見たほうがいいでしょう。
最後に。

菌糸ビン飼育は、最初は難しそうな印象ですが、やってみれば意外と簡単にできます。
だれでも「初めて」はあります。
まずは始めてみることが大切です。
マット飼育よりも費用はかかりますが、数が少なければそれほど高いわけではない(800ccで300~500円)ので、チャレンジするメリットは充分ありますよ!
おすすめの菌糸ビン。
こだわりのSRDシリーズ!安くても品質はバッチリ!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
クワガタのマット飼育のやり方はこちら! こんにちは。ケンスケです。わが家にはクワガタの幼虫がたくさんいます。オオクワガタコクワガタヒラタクワガタノコギリクワガタアカアシクワガタ全部成虫になったら、大変だ!とは思いつつも、全部の幼虫が[…] こんにちは。ケンスケです。子どものころ憧れだった「オオクワガタ」。いつか飼育してみたいと思いながら、いつの間にか大人(おじさん)になっていました。そんな少年の心も忘れかけていたある日。妻の実家からの帰り道で立ち寄[…] こんにちは。ケンスケです。初めてクワガタを飼育するときに気になるのが、飼育にかかる費用ですよね。お子さんがカブトムシ飼育を始めたのをきっかけに、親御さんのほうが昆虫飼育にハマってしまった!っていう話もよく聞きます[…] こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタを飼育していて欠かせないのが、マット交換。古いマットはカビが生えてきていたり、ダニやコバエが湧いたり、エサの昆虫ゼリーがこぼれたりして汚れています。さらに、夏[…]
オオクワガタ成虫の飼育・繁殖についてはこちら!
クワガタにかかる費用についての記事はこちら!
カブトムシ・クワガタのマットの処分はこちら!
菌糸ビン飼育について詳しく解説した記事です。 こんにちは。ケンスケです。 私が子供の頃、クワガタの幼虫を飼育するのは、なかなか敷居の高いものでした。というのは、現在のように飼育方法が確立されておらず、「材飼育」が基本となっていたのです。「材[…]