こんにちは、ケンスケです。
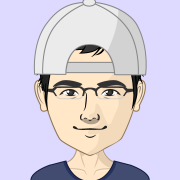
夏季にクワガタの採集に行くと、クワガタがペアで仲良く樹皮でみつかることがよくあります。
飼育をしているときは、基本的に別々に飼育するのですが、ペアリング(交尾させる)ケースでは仲良く一緒に隠れている光景もよく目にします。
この行動は、「メイトガード」といいます。
オスがメスにかぶさるようにいることを「メイトガードポジション」っていったりもしますね。
今回の記事は、クワガタの「メイトガード」についてみていきましょう。

『クワガタの「メイトガード」オスがメスを守る行動は遺伝子を残す戦略!』
「メイトガード」って何?

メイトガードとは、クワガタのオスが同種のメスを守ろうとする行動のこと。
クワガタは交尾した相手を同種・異種の生物から守る行動をします。
野外で採集するときにペアで見つかることが多い理由が、メイトガードしているためなんですね。
飼育していて、オスがメスの上に覆いかぶさるような姿(交接器はでていない状態)がみられたら、交尾は完了している証拠。
仲良くしているようにみえますが、あまり長く同居させていると、どちらかが攻撃してしまうこともあります。
メイトガードがみられて、別々の行動をとり始めたら速やかに別居させましょう。
でも、見た感じでは仲良しなので、引き離すのも躊躇しちゃいますよね。
オスがメスを守る行動「メイトガード」の理由。

他の昆虫の多くは、交尾が終わるとすぐに別々の行動をしたり、オスがメスに食べられてしまったり(カマキリなど)しますよね。
どうしてクワガタは「メイトガード」をするのでしょうか?
答えは、
自分の子孫を残したい!
ですね。
ご想像の通りだったかもしれません。
クワガタのオスが同種のメスと出会う場所は、ほとんどがエサ場。
そう、樹液の出ている場所です。

樹液場には、同種のオス・メスだけでなく、違う種類の昆虫、さらには鳥やタヌキなどの天敵もやってきます。
クワガタのオスにとっては、敵だらけ!ってわけ。
オスは自分の子をメスに無事に産卵してほしいのです。
交尾したメスには充分な栄養をとってもらわなければなりませんね。
別の種類のクワガタやカブトムシ、スズメバチなどに樹液場を追われるようなことがあれば栄養不足になってしまうかもしれません。
闘争によるケガも心配です。
カラスやフクロウなどの天敵に襲われる危険だってあります。
たまにペアリングケースを除いてみるとメイトガードポジションのままメスがエサを食べているのをみかけることがあります。
オスはメスが安心して、栄養を摂るのをサポートしているんですね。
心配事はもうひとつ。
敵は異種だけではありません。
同種のオスです。
クワガタは自分の遺伝子を残そうと隙きあらば、メスと交尾をしようと狙っています。
クワガタは交尾後すぐに受精するわけではないといわれています。
受精する前に他のクワガタと交尾してしまうと、精子が混ざってしまう可能性もありますよね。
そのために自分のパートナーを他のオスから守らないといけないのです。
「メイトガード」は、交尾する機会の少ないクワガタが自分の子孫を残すための戦略のひとつだったんですね。


コオイムシという昆虫は、交尾したメスがオスの背中に卵を産みつけます。
オスは卵が孵化するまで、背負い続けて卵を守ります。
子供を背負うので「子負虫」(こおいむし)ですね。
カブトムシの子孫を残すための戦略とは?

クワガタは自分の交尾相手を守ることで、自分の遺伝子を次世代に残すという戦略をとっています。
では、クワガタの永遠のライバル、カブトムシはというと、
「メイトガード」はしない!
カブトムシはクワガタと違って、オスがメスを守るような行動をしません。
むしろ、交尾が済んだ相手のメスを投げ飛ばしたりするのです。
なぜかというとカブトムシは・・・、
多くのメスと交尾することで自分の遺伝子をばらまく!
カブトムシは交尾相手を樹液場で見つけます。
交尾をした相手のメスが長く居座っていては、他のメスが近づけないかもしれません。
ということで、交尾が済んだ相手を投げ飛ばして、追い払うのです。
そうして、樹液の甘い匂いに釣られてやってきた次のメスと交尾するのです。
カブトムシがクワガタの戦略が違う理由は、
クワガタよりも生息数が多く、数少ない樹液場を張っていれば相手を見つけやすいですね。
②カブトムシを脅かす生物は少ない!
カブトムシはメスといえども他の昆虫に比べて、体格が大きく力も強いのです。
あのスズメバチでさえも手を出せないほど。
守ってあげる必要がないほど強いのかもしれませんね。
クワガタとカブトムシ。オスのメスに対するふるまいの違いについてはこちらの本で詳しく紹介されています。 こんにちは。ケンスケです。カブトムシとクワガタ。どっちが強いと思いますか?やっぱり、大きさで勝るカブトムシ!いやいや、俊敏に下から挟んでしまえばクワガタでしょう!そんな議論を少年のころ友達と話していた記憶[…]
カブトムシとクワガタのオスのふるまい方の違いは、両者の生態からくるものだったんですね。
戦略は違いますが、両者とも「自分の遺伝子を多く残す!」ことに命をかけているのです。
おもしろいでしょ。
クワガタのオスがメスを攻撃するのはなぜ?

クワガタのオスは、交尾相手を守る!
というのが、「メイトガード」でした。
ですが、よくクワガタの繁殖でいわれる「メス殺し」。
とくにヒラタクワガタの種類で多くみられます。
これはどうして起きるのか気になるところですよね。。
クワガタのオスはメスをいつまでガードし続けるのでしょうか。
クワガタのメスは交尾後、数日から1週間ほどじっとして、産卵のために栄養を蓄えたり、体力を回復させたりしてから産卵する場所を探しにいきます。
オスはその間は他のオスが寄り付かないようにガードしていると考えられています。
自然界では、メスがオスのもとを去った後は再び出会うことは稀です。
でも、人工的なペアリングのためのケースは小さいものが使用されます。きちんと交尾が行われるようにメスが隠れる場所を制限するためです。
ということは、
↓
「メイトガード」
↓
メスが行動を開始(ガードが解ける。)
↓
産卵場所を探すが、ケースが狭い。
↓
オスは再び目の前に現れたメスに交尾を迫る。
↓
メスはすでに交尾済みなので、拒否する。
↓
メスが逃げようとするので、大アゴで強く抑え込む。
クワガタは交尾する際にメスを大アゴで軽くはさむ行動をとります。
逃げないようにしているのか、態勢を整えるためか、交尾の合図なのかはわかりません。
「メス殺し」という事故は、この軽く大アゴではさむ行動がメスの強い拒否によってエスカレートすることによって起きていると考えられますね。
逆に、オオクワガタの種類では、メスがオスを捕食してしまう事故も起きることがあります。
これは、産卵セットにオスも同居させてしまっているときに起きていることが多いです。(もちろんペアリングセットでもありえます。)
産卵でタンパク質が不足したメスがオスを捕食してしまうのです。
なので、産卵前のメスにはタンパク質が重要です。
ペアリングの注意点。

これらの生態を見ていくと、繁殖を狙うときのペアリングで気をつけるポイントが見えてきますね。
○「メイトガード」がみられたらオス・メスの別居開始。
○メスにはタンパク質多めのエサを与えておく。
こんにちは。ケンスケです。コクワガタは、全国各地の雑木林に生息していて、生息数も多いので、手に入れやすいクワガタです。長生きするし、丈夫で適応範囲も広いので初めての方でも飼育しやすい入門種といえます。自然の多い地[…]
こんにちは。ケンスケです。クワガタを飼育していると、どうしても避けて通れないことがあります。足の欠損(けっそん)クワガタのいずれかの足がなくなってしまうことですね。足がとれたからといって、すぐに死んでしまうような[…]
最後に。

クワガタの「メイトガード」という行動は、人間の目でみると「紳士的」と映るかもしれません。
ですが、その行動の意味を考えてみると、実に理にかなった生存戦略だったりします。
クワガタの生態をみていると飼育に役立つ情報がたくさん得られます。
よ~く観察することが、飼育が上達する秘訣なのかもしれません。
そして、生き物飼育は、わたしたちの住む地球を知る手がかりにもなるのです。
生き物たちのちょっとした行動の意味を知っていくことで、地球環境を見直すきっかけにもなりますよね。
こちらの本は、私たちの大好きなカブトムシやクワガタたちが夜の雑木林でどんな行動をしているのかを研究した本です。
おもしろいのでぜひよんでみてくださいね。
| カブトムシとクワガタの最新科学 | ||||
|
最後まで読んでいただきありがとうございました。
クワガタの「死んだふり」。どんな習性? こんにちは。ケンスケです。クワガタを飼育していると・・・あれ?固まって動かない!死んでしまったのかな?という経験はありませんか?でも、私の心配をよそに、しばらく経つと元気に動き出していることがほとんど。カ[…] こんにちは。ケンスケです。クワガタっていろんな種類がいます。日本にいるクワガタだけで30種類以上ともいわれています。カブトムシは成虫として越冬はできないけれど、クワガタの中には越冬して次の年の夏にも成虫として活動でき[…] こんにちは。ケンスケです。飼育しているクワガタ。少しでも長く生きていてほしい!自分で繁殖から羽化までさせたクワガタなら、なおさらそう思いますよね。でも、ムシの一生は短い!まぁ、短いとはいっても、国産クワガタは5年[…] こんにちは。ケンスケです。クワガタを飼育しているとよく見かけるひっくり返っている姿。木に登るのが得意なはずなのに、どうしてすぐ落ちるのでしょうか?そこには、クワガタの習性からくる理由があるんです。今回の記[…] こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタを捕まえたいときに見る場所といえば・・・、樹液の出ている木!そう、正解です。木が樹液を出すしくみを理解して自然保護を考えてみよう![sitecard subt[…] こんにちは。ケンスケです。梅雨をむかえる頃になると虫たちが、動き出しますね。私たちが大好きなカブトムシやクワガタたちも活動が活発になります。カブトムシやクワガタを採集したいなら「樹液の出ている木を探せ!」[…]
クワガタってどれくらい生きるの?
どうしたらクワガタは長生きする?
クワガタ飼育に登り木を入れるのはなんで?
カブトムシやクワガタが光に集まる理由は?
木が樹液を出すのはなんで?
カブトムシやクワガタの「後食」ってな~に?
こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタが蛹から羽化したら嬉しいものですよね。ついつい触ってみたり、持ち上げてみたりしてみたくなっちゃいます。でも、ちょっと待ってください!羽化後まもなくは、まだ身体[…]
クワガタの人工蛹室が必要なときってどんなとき?
こんにちは。ケンスケです。クワガタを飼育しているときに気になっていたのが「人工蛹室」。クワガタが蛹から羽化して成虫に変化する様子を見てみたかったんです。でも、どこの飼育の方法を読んでも「蛹の時期は触っちゃダメ!」[…]
クワガタ成虫の冬眠準備!
こんにちは。ケンスケです。国産のカブトムシはほとんどが寒い冬を越せずに寿命を迎えます。でも、国産クワガタの中には冬眠(越冬)をして春を迎え、次のシーズンにも活動する個体がいます。とはいっても、冬はクワガタにとって[…]

















