こんにちは。ケンスケです。
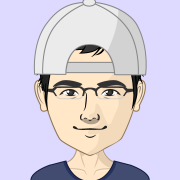
は~るがき~た~、は~るがき~た~、ど~こ~に~きた~♪
カブトムシを卵から育てている方は、幼虫が羽化するのが待ち遠しいですよね。
寒い冬を乗り切ったら、カブトムシにとって大事な季節がやってきます。
越冬明けには何をしたらいい?
羽化までの準備はなにをしたらいい?
せっかくカブトムシを飼育しているので立派なカブトムシの成虫に育てたい。
そんなあなたに読んでほしい。
今回は
『カブトムシ幼虫飼育。春が来たらやっておくこと!大きな成虫に育てよう。』
です。
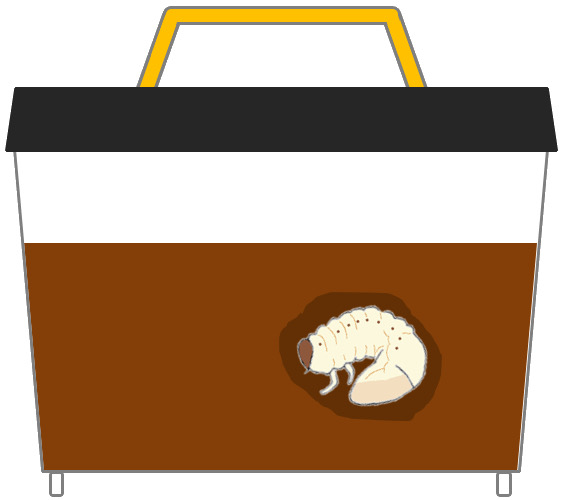
カブトムシのライフサイクルを確認しておくとわかりやすいですよ!
こんにちは。ケンスケです。夏になると人気のカブトムシ。最近は子供だけじゃなくて、大人になって飼育を楽しむ人も増えてきているように感じます。そこで、もうすでにご存知かもしれませんが、カブトムシのライフサイクルをおさ[…]
○3月初めにはマットを新しいものに交換する。
○できれば4月終わりごろにもう一度交換する。
○幼虫をよく観察する。とくに皮膚の色!
○交換するマットの水分調節は慎重に。
○5月になったらマットも幼虫も触らない!
○複数飼育している場合は羽化してきた成虫は別に移す
少し難しそうですが、ここからが大事な時期です。
一度成功してしまえば簡単ですので挑戦してみてください。
カブトムシを大きく育てる方法を紹介しています。
こんにちは。ケンスケです。最近、読者の方から「カブトムシの記事ばっかりじゃん!」って怒られました。というわけで、今回もカブトムシの記事いってみましょう!だって、カブトムシの記事が最近人気なんです。やっ[…]
それでは、詳しく説明していきましょう。
越冬明け!気温が12℃を超えると動き出す!

冬の間、ほとんど動かずに過ごしてきたカブトムシの幼虫たち。
春を迎えると少しずつエサ(マット)を食べ始めます。
気温が低い間は、秋までに蓄えた栄養を使って生きています。
この越冬明けの時期は、失った体重と栄養を取り戻す時期です。
だいたい5月中旬から6月ごろにかけて、幼虫たちは蛹になる前の段階である「前蛹」に変態します。
そのまえに「蛹室」(ようしつ)を作ります。
蛹室はカブトムシが蛹(サナギ)になる空間で、羽化(うか)[成虫になること]して、身体が固まるまでそこでジッとしています。
蛹室は幼虫のフンと体液で壁を固めて細長い形に作られます。
このときに幼虫は自分の水分と体力を使うのです。
さらに、前蛹になると移動も食事もできなくなります。
前蛹になってから羽化して成虫としてエサを食べるまで、1ヶ月以上もの間何も口にしないのです!
なので、越冬明けに大切なのが、
水分補給
なのです!
カブトムシの~令幼虫ってな~に?どうやって見分ける?
こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタの幼虫って、孵化したてはほんとにちっちゃいですよね。でも、冬が明けてマット交換をしてみると長さも10センチを超えるぐらいの大きさになっていてびっくりしたことはありませんか?[…]
3月ごろにはマットを新しいものに交換する。

冬季、カブトムシは動く&フンもする!
よく「カブトムシの幼虫は冬眠する」って聞きますよね。
でも実はこれ、完全に冬眠しているわけではないんです。「越冬」っていいます!
冬の寒い時期に飼育ケースをよく観察していると、前日にケースの側面に見えた幼虫が次の日には見えなくなっていることがあります。
私は北側の部屋でカブトムシを飼育してるので、その部屋は昼間もあまり気温が上がりません。
ってことは、
完全に仮死状態のようになって眠っているわけではないんですね。
冬が来る前に替えたマットも気温が上がる頃になるとずいぶん減っているのがわかります。
幼虫がエサとして食べているんです。
ってことは、
もちろんフンもします。
春になってケースを開けてみるとフンだらけだったこともあります。
気温が12~13℃を上回ってくる日が増えてくると幼虫たちはマットをまたモリモリ食べ始めます。
冬がくる前に幼虫たちは大きく成長して冬を迎えるのですが、春になってもう一段階大きく成長します。
古いマットにはフンやダニ、コバエなども増えてきていて、大事な幼虫が病気になりやすいので、ここは一気に新しい清潔なマットに取り換えましょう。
※古いマットは花壇などにまく人もいますが、できるだけ自治体の指示に従って廃棄してください。害虫が発生したり地域の生態系を崩さないようにするためです。
【カブトムシ・クワガタ】死骸やマットの処分。地域の生態系を守ろう!
こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタを飼育していて欠かせないのが、マット交換。古いマットはカビが生えてきていたり、ダニやコバエが湧いたり、エサの昆虫ゼリーがこぼれたりして汚れています。さらに、夏[…]
この時期にはオスとメスを見分けることができますよ!挑戦してみよう!
こんにちは。ケンスケです。カブトムシがたくさん産まれて、幼虫を知り合いのお子さんにあげたのはいいものの、オスばっかりだった・・・。メスばっかりだった・・・。な~んてことはありませんか?そう、私もちょっと前まで[…]
⇒【カブトムシ】幼虫。初心者でも簡単。マット交換と育て方を紹介!
できれば4月終わりごろにもう一度交換する。

3月後半から4月中は幼虫たちがマットをたくさん食べる時期です。サナギに変わるための栄養を取り入れるためです。
カブトムシマットの中身はほぼ土。それほど栄養があるわけではありません。
そのためマットをたくさんの量を食べることで栄養を摂取しています。
そして、この時期が最後のマット交換です。
このマットを食べてサナギになります。そしてこのマットの中で蛹室(サナギを作る空間)を作ります。
サナギの時期は無防備で、カビや病原菌にも弱いです。
ということから、サナギになり始める前のこの時期に新しいマットに交換してあげましょう。
屋外では早い個体だと5月末に活動していることもあります。逆算すると5月頭ごろにはサナギになっている計算です。
なので、
4月最後の週には交換を済ませておきたいところです。
マットの量は飼育ケースの底から15㎝以上にしてください。
日本のカブトムシは蛹室を縦長に作ります。オスの蛹室は10㎝以上になるためです。
この時期のマットの深さは大事です!カブトムシのマットの深さはどれぐらいがいい?
こんにちは、ケンスケです。カブトムシ飼育で悩むのが、マットの深さ!今まではあんまり気にしてはいませんでしたが、わが家では毎年大量のカブトムシが孵化(ふか)してくるのです。こうなると深刻なのが、マットの量。カブ[…]
このときのマット交換時のポイント!
マットを軽く押し付けて固める!
大きな木クズは取り除く!
カブトムシがサナギになるときに、キレイな蛹室を作るためにやっておくと羽化不全のリスクを減らすことができますよ!
飼育ケース内の密度はできれば1頭に対して1ℓ~2ℓ以上は欲しいです。
羽化不全のリスクを減らすには?
こんにちは。ケンスケです。カブトムシを飼育していて、無事に蛹になったぁ~!!!と喜んでいたのもつかの間。なかなか成虫に羽化しない!羽がうまく閉じられない!羽がゆがんでしまった!角が曲がってしまった!羽[…]
幼虫をよく観察する。とくに皮膚の色!

冬から早春の時期のカブトムシの幼虫の色は「青みがかった白」「少し透明な白」です。身体はパンパンにふくれ上がっているような感じになります。
これからサナギになる時期になってくると「黄色」がかってきます。サナギに近づけば近づくほど黄色が濃くなる印象です。
そして、前蛹段階(サナギになりかかり)になると皮膚に少ししわが出てきて、身体はブヨブヨしたような感触になります(本当は触ってはいけません!)。透明感はなくなってきます!
もし万が一、マット交換のときに前蛹段階の幼虫がいたら、そのままマットには戻さずに「人口蛹室」をつくってください。
カブトムシは前蛹段階になると動くことができず、蛹室を作り直すことができないからです。
1.トイレットペーパーの芯の下にキッチンペーパーを湿らせて折り畳む
2.絶対に倒れないように固定する
3.前蛹段階の幼虫を入れる
4.絶対安静を保つ
5.乾燥に注意
 上はコーヒーの空き瓶にキッチンペーパーを敷き、上にトイレットペーパーを載せています。倒れにくいしちょうどいいサイズでおすすめです!
上はコーヒーの空き瓶にキッチンペーパーを敷き、上にトイレットペーパーを載せています。倒れにくいしちょうどいいサイズでおすすめです!
他にも身近で代用できるものもたくさんあります!


100円ショップで購入した細長いグラスや醤油さしなどで人工蛹室をつくってみました!透明だから観察しやすい!
倒れないように要注意です。
カブトムシの蛹の育て方!
こんにちは。ケンスケです。カブトムシの幼虫を飼育している期間、いちばんデリケートなのが、「蛹(サナギ)」カブトムシが長~い10か月もの幼虫期間から、あのカッコいい成虫の姿に変身するメチャクチャ不思議な時期です。[…]
交換するマットの水分調節は慎重に。

マットは幼虫にとってエサであると同時に蛹室を作る壁にもなります。
幼虫はサナギになる前に自身の体液で周囲のマットを固めて蛹室を作ります。
このとき乾燥しすぎると壁が崩れてしまったり、固めきれないことも考えられます。
逆に水分が多すぎても崩れてしまったり、カビが発生してサナギがカビに巻かれてしまうこともあります。蛹室の中に水が溜まってしまうことも。
この時期は特に水分量に注意しましょう。
〖軽く握って固まり、水がしみだしてこない程度〗
です!
カブトムシ飼育をしていてトラブルはつきもの。そんな時は冷静に対処しましょう!
カブトムシの水やり。湿度を保つことは重要です。
こんにちは。ケンスケです。カブトムシの飼育では、幼虫でも成虫でも「水やり」が欠かせない作業ですよね。でも、カブトムシを初めて飼う人にとっては、どれくらいの量をあげればいいのか、どれくらいの頻度で行うのかわからないことも多[…]
5月になったらマットも幼虫も触らない!

5月も中ごろになってくるとぼちぼち幼虫も前蛹になり始めます。非常にデリケートな時期ですので極力触らないようにしましょう。
6月に入るとサナギになっていることが多いのでむやみにケースを持ち上げたりせず静かに見守りましょう。
(振動や騒音は厳禁!)
透明なケースで飼育している場合は側面からサナギの様子が見られるかもしれませんね。
とくにサナギが白っぽい時期は、中身は神経系を残して他はドロドロの液状ですので、この時期に衝撃や傾けるなどの刺激を受けるとそのまま☆になってしまうこともあるので注意してくださいね。
サナギは動かしたりするとモゾモゾ動いて、鳴いたりします。触ってみたくなる気持ちも分かりますが安静にしてあげてください。
5月は暑い日も出てくる時期です。
カブトムシは夏の虫といっても、できるだけ30℃以下になる場所で飼育しましょう。
置き場所は
振動のない静かな場所
なるべく光の入らない場所
こんにちは。ケンスケです。カブトムシを飼育したり、採集したりして不思議に思っていたことがあります。カブトムシの色!!!多くが「黒っぽい茶色」よく見るのが「明るめの茶色」たまーに見るのが「赤っぽい茶色」ごくたま[…]
こんにちは。ケンスケです。カブトムシの幼虫を飼育している期間、いちばんデリケートなのが、「蛹(サナギ)」カブトムシが長~い10か月もの幼虫期間から、あのカッコいい成虫の姿に変身するメチャクチャ不思議な時期です。[…]
複数飼育している場合は羽化してきた成虫は別に移す。

同じケースで複数を飼育している場合、6月も後半近くになると羽化してでてくる成虫とまだサナギ状態の個体が混在することになります。
成虫になったカブトムシがマットに潜ったときに他の個体の蛹室を壊してしまうこともあります。
蛹室を壊されたサナギは羽化不全といって、きれいな成虫の形にならなかったり、最悪羽化できなかったりもありますので、地上に出てきた成虫は別のケースに移してください。
また、いつの間にか、羽化した成虫どうしがペアリング(交尾)してしまっていることもあるので注意が必要です。(必要以上に産卵させてしまう可能性があります。)
こんにちは。ケンスケです。カブトムシを飼育していて、無事に蛹になったぁ~!!!と喜んでいたのもつかの間。なかなか成虫に羽化しない!羽がうまく閉じられない!羽がゆがんでしまった!角が曲がってしまった!羽[…]
こんにちは。ケンスケです。カブトムシに「エサ台(エサ皿)は必要か?」という質問をよく受けます。私は、あったほうがいいと考えています。もちろん、なくても充分に飼育することは可能です。ですが、あったほうが手間、コ[…]
こんにちは。ケンスケです。カブトムシは飼育するのに、難しい知識や特別な道具が必要なわけではありません。だれでも簡単に育てることができる生き物です。でも、生き物ですから、たまにはうまくいかないことも失敗して[…]
こんにちは。ケンスケです。カブトムシは、卵で2週間。幼虫で9カ月。蛹で1か月。合わせて約10か月~11か月かけて、やっと成虫になります。カブトムシは秋に生まれてからず~っと土の中で過ごして、6月~7月にかけて羽化。[…]
こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタが蛹から羽化したら嬉しいものですよね。ついつい触ってみたり、持ち上げてみたりしてみたくなっちゃいます。でも、ちょっと待ってください!羽化後まもなくは、まだ身体[…]
まとめ

寒~い冬を乗り切ったら、カブトムシの幼虫はもっと大きくなって蛹になる準備をする季節です。
越冬明けから5月ごろまでがカブトムシの幼虫にとっての大切な期間。安全に羽化を迎えられるように準備をしておきましょう。
たくさん注意事項があるようですが、大丈夫!カブトムシは元来、丈夫な生き物です。
暖かくなった梅雨頃にはきっと無事に羽化してくれるはずです。
カブトムシ成虫飼育【まとめ】
こんにちは。ケンスケです。梅雨の時期から夏にかけての時期は、カブトムシが成虫として活動する季節ですね。1年近く幼虫で過ごしたカブトムシたちが、子孫を残すために姿を変えて地上に降臨します。そんなかわいくて、カッコい[…]
カブトムシ幼虫飼育のまとめ!
こんにちは。ケンスケです。子供のころカブトムシを育てたことがある方は多いですよね。そんな方も育て方を忘れてしまっていることもあるでしょう。また、お子さんができて初めてカブトムシを育てる!っていう方もいると思います。[…]
カブトムシの飼育用マットの種類と選び方を紹介しています。
こんにちは。ケンスケです。カブトムシを飼育するのに多くの人が利用しているのが、「マット」(土)!!!でも、マットの種類ってたくさんあってどれを使っていいか分かりにくいですよね。今日は、カブトムシの成長ステ[…]
カブトムシの幼虫飼育。加湿には水道水をそのまま使ってもいい?
こんにちは。ケンスケです。カブトムシやクワガタの幼虫を飼育しているときに直面するのが、「水道水の残留塩素」問題。アクアリウムで熱帯魚やメダカ、金魚などを飼育しているときは、水道水をそのまま使うのではなく、塩素の中和剤を混[…]
カブトムシの飼育方法を季節ごとに紹介しています。
こんにちは。ケンスケです!ふ~ゆ~が~♪くるまえに~♪ということで、今回の記事は『カブトムシ飼育、冬が来る前にやっておくこと!』夏の終わりとともにいなくなったカブトムシ飼育セット。そのままにしておくといつの間にか・・[…]
こんにちは。ケンスケです。ふゆ~が~♪は~じまるよ~♪さてさて、カブトムシの幼虫たちは冬はどうしているのでしょうか?今回のテーマは『カブトムシの幼虫飼育・冬の管理編』です。カブトムシ成虫の寿命カブトム[…]
こんにちは。ケンスケです。多くの子供たちが好きなカブトムシ。カブトムシの最大の特徴は、そう「ツノ」です。カブトムシのツノはどうしてついているのでしょう?また、カブトムシを何頭か比べてみると体の大きさ、ツノの長さに[…]
こんにちは。ケンスケです。今でも大人、子供問わずに大人気のカブトムシ。カブトムシは幼虫の間、土の中で生活していますよね。しかも土を食べて成長しています。でも、土の中は雑菌がいっぱい!どうやってカブ[…]
立派な成虫が出てくるように愛情をもって育てましょう!
私はマットをいろいろ使っていますが、このマルカンのバイオ育成幼虫マットが状態もいいようで、使いやすいです。
カブトムシ用のマットを購入するときは、包装に「カブトムシ用」とか「カブトムシの絵(幼虫)」がプリントされているものを買いましょう!
次はカブトムシの成虫を飼育する!って方は、こちらの記事もおすすめです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。



























